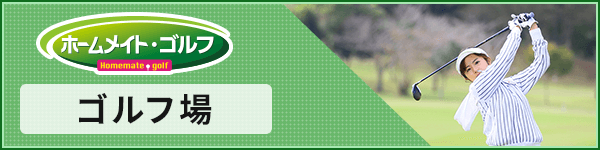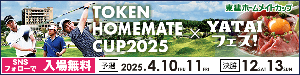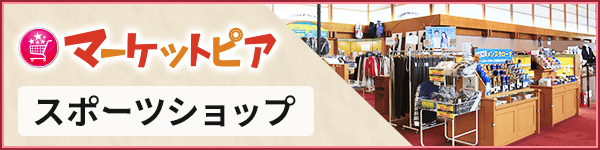コース管理課 可児です。
クラブハウス前の「どんぐり」達が少しずつ大きくなり始めました!
日本語で「どんぐり」とは、クヌギ・カシ・ナラ・カシワなどの果実の総称で、どんぐりは全てブナ科の果実となります。
日本に自生するブナ科の樹木は22種で、「どんぐり」は、まるっこい固い実で、帽子がついています。
帽子は難しい言葉で「殻斗(かくと)」と言われ、木の種類によって色々な形の帽子があります。
春に花が咲いて、秋にどんぐりになるものと、1年半後の秋にどんぐりになるものがあります。
今では、どんぐりを食用にする事は殆どありませんが、米を作る前の縄文時代では、どんぐりや栗などの木の実は、大切な主食だったそうです。
アクを抜いたどんぐりを細かくすりつぶし、土器で煮て、だんごやお粥のようにして食べていたそうです。
どんぐりは「団栗」と書き、名前の由来は諸説あり、実をコマにして遊んだことから、コマの古名「ツムグリ」が「ズムグリ」になり、「ドングリ」になったという説や、「どん・くり」で、どんくさい栗という説もあります。
栗のように美味しく使うことができない、栗のできそこないといった意味でしょうか。
どんぐり拾いでもしてみようかな。
★★★ ご来場をお待ちしております。 ★★★

クラブハウス前の「どんぐり」達が少しずつ大きくなり始めました!
日本語で「どんぐり」とは、クヌギ・カシ・ナラ・カシワなどの果実の総称で、どんぐりは全てブナ科の果実となります。
日本に自生するブナ科の樹木は22種で、「どんぐり」は、まるっこい固い実で、帽子がついています。
帽子は難しい言葉で「殻斗(かくと)」と言われ、木の種類によって色々な形の帽子があります。
春に花が咲いて、秋にどんぐりになるものと、1年半後の秋にどんぐりになるものがあります。
今では、どんぐりを食用にする事は殆どありませんが、米を作る前の縄文時代では、どんぐりや栗などの木の実は、大切な主食だったそうです。
アクを抜いたどんぐりを細かくすりつぶし、土器で煮て、だんごやお粥のようにして食べていたそうです。
どんぐりは「団栗」と書き、名前の由来は諸説あり、実をコマにして遊んだことから、コマの古名「ツムグリ」が「ズムグリ」になり、「ドングリ」になったという説や、「どん・くり」で、どんくさい栗という説もあります。
栗のように美味しく使うことができない、栗のできそこないといった意味でしょうか。
どんぐり拾いでもしてみようかな。
★★★ ご来場をお待ちしております。 ★★★