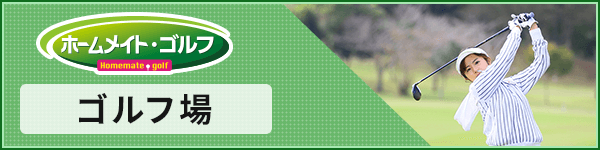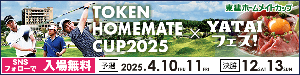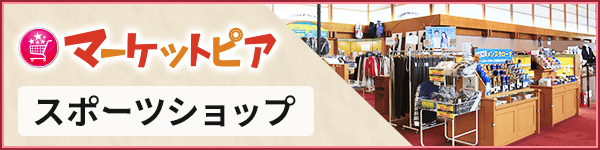コース管理課 可児です。
写真は、ユリ科の『ナルコユリ(鳴子百合)』です。
植栽場所は、南東コース1番です。
地下茎で横へと増えていき、白い線が葉っぱに入っていて、斑入りアマドコロという呼ばれ方もします。
ナルコユリとアマドコロは姿がそっくりでぱっと見で判断が付きにくい植物です。
アマドコロは茎にゆるい角が付いているので、茎をつまんでくりくりすると指の腹に引っかかるような触感があり、茎を切ると断面がいびつな多角形のようになっています。
ナルコユリは茎の断面が円形で茎をさわっても引っかかりがありません。
他にも花の付け根の形状の違いなどもあるようで、まるで間違い探しのような小さな違いですが、可能であれば茎をさわって確かめるのが一番わかりやすいと思います。
その茎の違いから「まるこゆりにかくどころ」(ナルコユリ→茎がまるい:アマドコロ→茎がかくばっている)と語呂合わせで憶えたりします。
ナルコユリの根茎を日干ししたものを茶菓として利用した、ナルコユリ茶は、「黄精」と呼ばれ、昔から生薬として重宝されてきました。
高麗ニンジンに匹敵するほどの滋養強壮効果があるといわれ、疲労回復や食欲不振改善などにも効きます。
開花時期は、4月〜6月です。
ぜひ、ご覧ください。
★★★ ご来場をお待ちしております。 ★★★

写真は、ユリ科の『ナルコユリ(鳴子百合)』です。
植栽場所は、南東コース1番です。
地下茎で横へと増えていき、白い線が葉っぱに入っていて、斑入りアマドコロという呼ばれ方もします。
ナルコユリとアマドコロは姿がそっくりでぱっと見で判断が付きにくい植物です。
アマドコロは茎にゆるい角が付いているので、茎をつまんでくりくりすると指の腹に引っかかるような触感があり、茎を切ると断面がいびつな多角形のようになっています。
ナルコユリは茎の断面が円形で茎をさわっても引っかかりがありません。
他にも花の付け根の形状の違いなどもあるようで、まるで間違い探しのような小さな違いですが、可能であれば茎をさわって確かめるのが一番わかりやすいと思います。
その茎の違いから「まるこゆりにかくどころ」(ナルコユリ→茎がまるい:アマドコロ→茎がかくばっている)と語呂合わせで憶えたりします。
ナルコユリの根茎を日干ししたものを茶菓として利用した、ナルコユリ茶は、「黄精」と呼ばれ、昔から生薬として重宝されてきました。
高麗ニンジンに匹敵するほどの滋養強壮効果があるといわれ、疲労回復や食欲不振改善などにも効きます。
開花時期は、4月〜6月です。
ぜひ、ご覧ください。
★★★ ご来場をお待ちしております。 ★★★